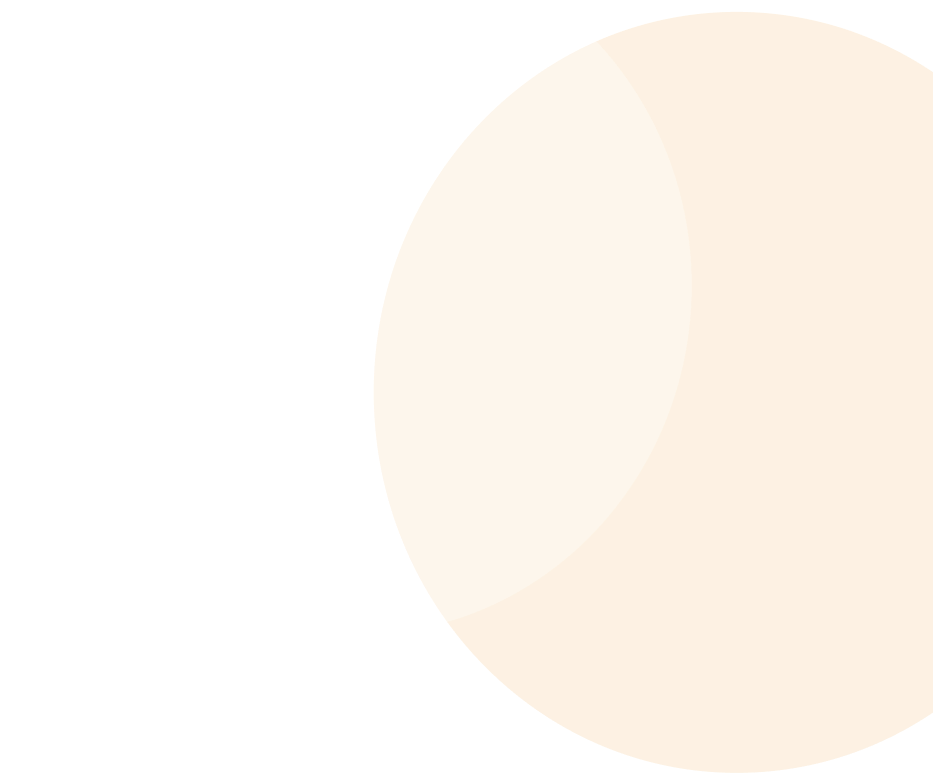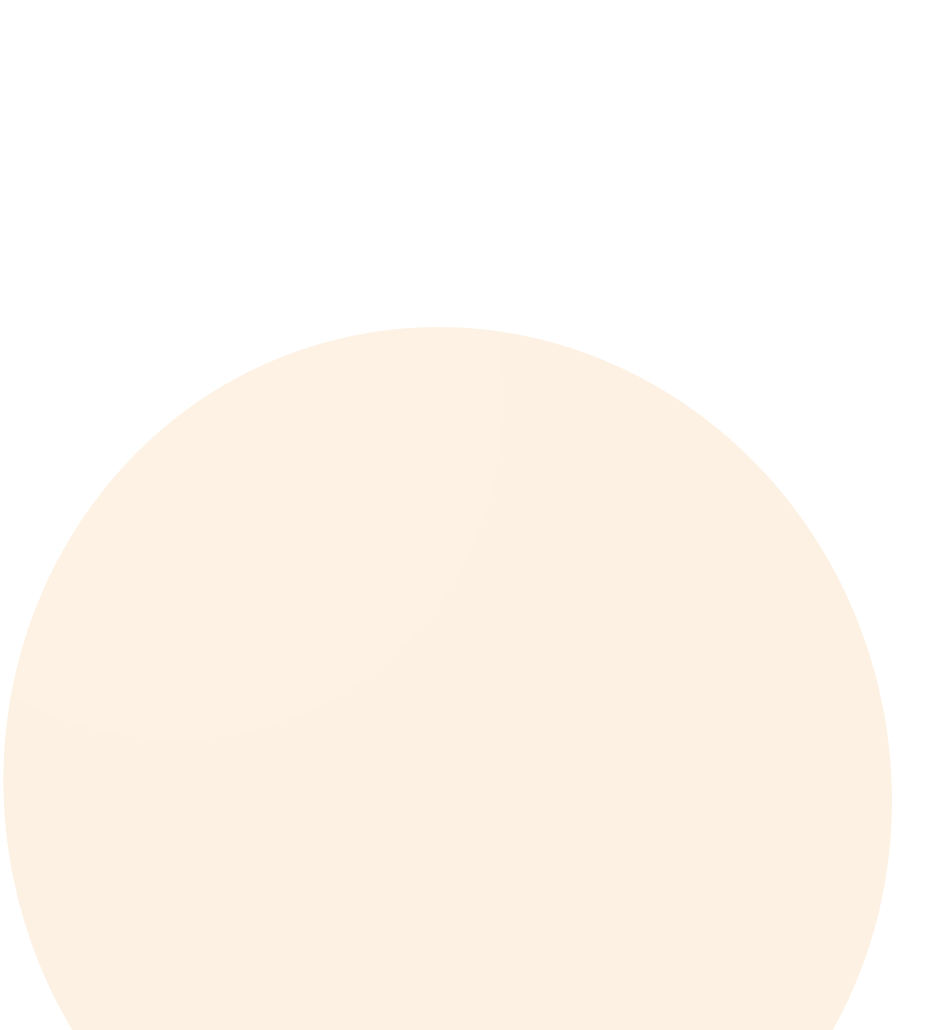まずは今回のインターンシップでIITs生に任せたプロジェクトの概要を教えてください
小林さま:当社は、「くらし」と「はたらく」を自由にデザインできる社会の実現を目指すワークテック企業です。会社全体として、多様な働き方で生じる「オフィス」と「組織」の課題解決をミッションとしています。
そのなかで今回は、会議室に関連した以下の課題への解決策として、IITs生にAI・IoTの技術を使用したプロダクトを提案・開発してもらい、最終的な成果発表を行うというプロジェクトを設定しました。
オンライン会議が増え、会議室稼働率が上昇することにより起こる3つの課題
- 予約時の会議室の空き状況により、1人での利用にもかかわらず大人数用の会議室が予約されているなど、参加人数に適した会議室が予約されてない
- 使用が確定していない段階で予約されている。その予約の解除忘れが発生していたり、解除が直前で、会議室に空きはあっても他の人が利用できない
- 各会議間に空き時間がない予約状況で、先の会議が予定通りに終了しないことで、次の利用者が会議を始められない
学生の取り組み方やプロジェクトの進行過程はどのようなものでしたか
戴さま:まず、アイデアが出てくるのが非常に早く、また具体的でした。そのため、課題の解決手段自体はすべて学生から提案してくれたものをもとに進めました。こちらからは、初めに基本的な方向性を伝えた以外には、業界の慣習や、日本社会により適したものにするためのアドバイス、オプションとして他にどんなことができるかといったことを伝える程度でした。
小林さま:私からは、限られたコストやキャパシティのなかでできること、ビジネス視点で考えるべきことなどは補足しましたが、全体的には学生が主体性をもって進めてくれました。

インタビューを受けている小林さまと戴さま
今回はオンライン・オフライン併用型での就業となりましたが、コミュニケーションはどのように行っていましたか
戴さま:前提として、当社はオフィスに関連したSaaS型のプロダクトを開発する企業なので、自社においてもリモートワークを基本としています。そのため対面コミュニケーションが少ないと思われがちなのですが、その分オンラインツールをフル活用して、活発なコミュニケーションが生まれるように工夫しています。
現在は、Microsoft Teams、Google Meet、Discordを使用しています。会社に出社をする社員もいるので、その場合はもちろん対面でも話します。いろいろななツールを活用しながら、ちょっとした相談ごとで気軽にやり取りできるような仕組みになっています。
今回はスクラム開発と呼ばれる開発手法で進めたので、IITs生とはデイリースタンドアップミーティングでプロジェクトの現在地を確認しました。
当社では普段こういった固定のミーティングを設定する場合、1回10分とすることが多いのですが、今回はオンボーディングを兼ねて1回30分のミーティングをルーチンとして、進捗の確認や相談ごとを解消していました。
基本的にはIITs生から毎日の報告を受けてフィードバックという流れでしたが、お昼のミーティングで出たタスクに対して、夕方ごろには提案が来て、翌日の進め方を報告してくれていました。
さらにもっと早い場合には同日中にソースコードが全部書けていて、「明日の何時ごろには終わります」と言われることもあり、作業スピードは本当に超高速。とんでもないスピードで進んでいました(笑)
ミーティング以外の時間で、ちょっと確認したいことがある場合は、オフィスやオンライン上で声をかけて都度課題を拾っていったので、円滑に進められたと思います。

自分の意見を述べているIITインターン生A. V.さん
逆に、コミュニケーションに関して改善できたなと感じる点はありますか
戴さま:プロジェクト全体の構成として、キックオフミーティングではオンラインのホワイトボード機能を使って、プロジェクトの方向性とどこにエネルギーを注いでいきたいかを書き出し、すべて目に見える形で整理しました。
タスクの進捗状況も、付箋を1つ1つ次の過程に移動させるようなイメージで可視化し、どれが進んでいて、どれが遅れているか、常に認識をすり合わせるやり方で行いました。
この方法で進める中で序盤少しつまずいたのは、「日本での当たり前」を前提にしてしまっていたことです。具体的には、報連相やタイムスケジュールの管理です。日本では時間は守るもの、1分でも遅刻は遅刻と捉えるのが一般的ですよね。これがインド人にとっては当たり前でないことに気づきました。
でも、そのことに気づいてからは、こちらも伝え方を変えて、ミーティングに遅れそうなときには、事前に相談してもらったり、コミュニケーションツールのリマインド機能を活用したりして克服しました。
初めは朝一番にミーティングをしていたのですが、一緒に働く中で彼の場合は午後の方がパフォーマンスがあがることが見えてきたので、ミーティングをお昼の時間に変更すると、よりリラックスして様々な提案をしてくれるようになりました。それ以降は明らかにパフォーマンスがあがったので、うまくいったなと思っています。
自分たちにとって当たり前のことでも、言葉にしなければ伝わらないし、逆に正しく伝えれば理解してもらえる。これは単純なことですが大きな学びでした。

ディスカッションしている戴さまとA. V.さん
小林さま:不満や問題ではないのですが、今回はPoC的なプロジェクトで、既存のチームの一員として動くものではありませんでした。なので、誰かがつくったものを引き継いだり、逆に誰かに引き継ぐ前提で開発してもらったりということがなかったのですが、もしもそれをやろうとしていたら、少し大変だっただろうなとは想像しています。
IITs生の能力の問題ではなく、単純にコミュニケーションを取る相手も、ドキュメントや会議といったコミュニケーションツールも増えるためです。
このやり方は、細部を気にする日本人的な視点では、コミュニケーションのたびに気がかりなところが生まれていたと思うし、逆にIITs生からすると、何をするにもスピーディに進められないフラストレーションに繋がったのではないか思います。
そういう意味で今回は、創作的な側面の強い、独立したプロジェクトを進めてもらったことはとてもよかったと思っています。普段は、細かい部分まで気にかけるため、どうしても最高速度で前進とはいかないですが、今回は、どんどん前に進めて新しいものをつくるというスタイルだったので、お互いにストレスを少なくできました。
成果発表の様子はいかがでしたか
戴さま:一言でいうと、非常に優秀でした。
当日参加した社内のエンジニアメンバーからもいろいろな質問があって、専門性の高い部分を突っ込むこともありました。単純にソースコードの書き方だけではなく、「そもそもどうしてそうなるのか」「これを用いたらどうなるのか」といった数学的な質問もありました。これに対して、即興でホワイトボードに書き出して解説し、「だからこれはできる/できない」と論理立てて説明していたのには私だけでなく皆驚きました。
当社の代表も、ハイレイヤーのビジネスパーソンに投げかけるような概念的な質問をしていましたが、彼なりの考えをもって具体的に回答していました。到底学生とは思えない、プロフェッショナルのエンジニアレベルでした。

成果発表の様子
小林さま:発表態度についていうと、自信をもってとても堂々としていました。日本の学生では間違いなくこの雰囲気は出ないな、と思いましたね。
成果発表では、一部英語を話せる社員がディスカッションに参加していました。その場の雰囲気、海外の学生だから、英語だからと、いろいろな要因があると思いますが、とても活発なディスカッションになっていました。
普段おとなしい社員がしゃべっていて、こんなに積極的だったかな、と違う発見もありました(笑)。
一方で、エンジニアメンバーだけでなく、セールスサイドの社員も参加しており、前半はビジネス寄りの議題、後半はエンジニアリング寄りの議題というつもりで進めていたのですが、全体での活発な議論を行うには、テクニカルに寄ってしまい少し難しくなりすぎたかなという反省もあります。
参加メンバーには、成果発表に至るまでのプロセスは共有していなかったので、1つの疑問から議論を大きく広げていくことはあまりできませんでした。次の機会があればそういったことも目指してみたいという欲はありますが、総じて明るい雰囲気の中でいろいろな話ができた場になりました。
学生が日本で就業するにあたっての改善すべき点や課題、今後受け入れを検討される企業様へのアドバイスをお願いします
戴さま:日本で働くなら、日本の常識を身につけるということでしょうか。特に時間を守る意識です。今回当社に来てくれた学生にとっては時間の最小単位は30分刻みくらいがよかったのかなと思います。私自身も海外出身なので、気持ちはすごくわかるんですが、日本では、特に企業では1分、環境によっては30秒の差でも気にしますよね。当社には外国籍のメンバーもいますが、皆日本の商習慣に慣れています。例えば僕個人の肌感覚でいえば、1分以内の遅刻は許容範囲かなと思いますが、相手がそう思わない以上、遅刻は遅刻。インターン期間中、カレンダーに会議の予定があっても、時間通りに来ていないことがありました。小林の言う通り、いきなりチームに入って、共通のルールの中で機能するということは難しかったと思います。
小林さま:比較対象はありませんが、受け入れ企業として当社はおそらく、スムーズに進んだ方だと思います。企業によってはもう少し混乱したり、意思疎通ができないこともあるんじゃないかなと。
戴を中心に、初日のキックオフミーティングでプロジェクトのゴールや進め方をすり合わせて、同じ方向を向けたのが大きかったです。
これをもし普段のように、都度、手段やプロセスを相談するところから入っていたらなかなか苦戦しただろうなと…(笑)。なので受け入れ側は、英語が堪能な人や海外のカルチャーに慣れている人以外が担当するのであれば、いつもの方法に合わせようとしすぎると、行き詰ってしまうかもしれません。あくまでお互いのやりやすさをもとに、やり方を調和させていくことを念頭に置いて進められれば良いと思います。
それと、今回当社は隔日で週2回の出社、ほかはリモートという就業形態でした。もちろん担当する社員の英語力や、社内カルチャーにもよると思いますが、結果的に当社にはこれがちょうどよかったと思っています。
正直英語力の問題もあって、雑談含め毎日話しかけるのも割と難しくて、変な沈黙を作ってしまわないか心配な部分もありました。弊社の規模では週2回顔を合わせることで、お互いにつかず離れずのコミュニケーションができました。

話している小林さまとA. V.さん
続いてウェブスタッフへの要望もお願いいたします
小林さま:どこまで求めるかによりますが、IITs生の情報が事前にもう少しわかっていると嬉しかったなと思います。
当社は現状、英語が堪能な社員が多くはありませんが、それでもグローバルを目指したいということで模索中の段階です。そういう状況なので、本当はプロジェクトにかかわっていない社員にももう少し彼と話してもらいたかったのですが、プレゼンの場以外でカジュアルに話しかけるということはなかなかできませんでした。
ほかのメンバーからすると、近い距離で仕事をしていない分、やはりコミュニケーションのハードルは上がってしまうので、就業開始前にどんなことをした、日本ではどこに行った、どんなことに関心がある、といった何気ないことを事前情報として貰えれば、幾分やりやすかったかもしれません。
あとは、今後のためを思うとあったらいいなと思うのは、成功事例ややり方のパターンです。IITs生という人材の注目度でいうと、上のレイヤーの人が採用してみたくて現場に丸投げ、みたいなことは起こりうるだろうし、その状態で、ゼロからすべてを考えるのは、難易度も高いしストレスがかかります。時間に対する捉え方の件などは、割とあるあるなのかなと思うので、これまでの事例の中から自社にあった方法を選べるとイメージがしやすいと思います。
戴さま:今回、当社が海外から直接人材を受け入れるのは初めてでした。海外から来た人が働くのに、どんな規制や注意点があるのか。こういうことがわかるのは社内で私くらいだったので、事務的な部分の説明が詳細にあると良いなと思いました。例えばビザの取得にかかる時間的なバッファや、来日前後に企業側で準備していたことの事例や統計があれば助かると思います。
今回、開始日がぎりぎりまでわからず、当社の新オフィスへの移転とも時期が重なり、かなりドキドキしたので、もう少し余裕をもって受け入れ準備を進められたら、もっと面白いこともできそうという期待も込めて、ぜひお願いします!
最後に学生への満足度
戴さま:エンジニアとしての視点で90~95点くらいあげたいです。想像していた以上にパフォーマンスは素晴らしかったです。一方で、お互いに初めてのことも多かったせいではありますが、時間の管理やコミュニケーション面でフィットしていない部分もあり、まだまだ改善できるので5~10点はそのための余白として残しておきます。
仮に今後、当社の開発チームに入ってもらえたとして、普段の開発業務をやったり、ほかのメンバーともやり取りが増えていけば100点になるポテンシャルは十分にあると思っています。また新しいことに挑戦するパッションがあって、提案する前向きな姿勢がチームメンバーに伝播していくことを思うと期待値が高いです。
小林さま:2段階くらい改善点があるということで80点ですかね。2段階が何かというと、日本において、日本企業で働くということでは、戴の言ってくれた改善点。あとは学生なので、発展途上の部分が残るのは当たり前と言えば当たり前ですが、発表の時に、どういう相手に何を伝えたいスライドかという部分はもっとクオリティをあげていけるし、それを求めても応えられる人材だと思いました。
普段の仕事だったら、セールスと話すときにはセールスが気になっている部分が明確になるように資料を作って、そこにフォーカスした説明をする。CTOや経営層と話すときはまた違ったところをフィーチャーして話す。
学生に求めるには厳しい水準だと思っていますが、一人前のビジネスパーソンになるには、もしくはその基準で考えると、ここは改善できるという意味での80点とします。敢えて言うなら、ですけどね。

Acallの皆さんとA. V.さん